ショパンのワルツ9番、Op69-1「別れのワルツ」を録音した。
結構前のこと、実家に帰ったときに楽譜があったので初見で弾いてみたら結構弾けたので、思ったより簡単な曲だという認識があった。
それで、なにかショパンの曲を弾こうかなってなったときに思い出して弾くことにした。簡単な曲とは言っても僕の技術が拙いせいで弾けるようになるのに結構時間がかかる。あまり真面目に練習してないだけかもしれないけど。
楽譜はナショナルエディション英語版の後期バージョンを使った。日本語版にリンクしている。一部から色々問題があると言われているが僕の英語読解力では多分違いがわからない。ナショナルエディションはよくある楽譜とは多少音が異なるけど、あまり重要とは思わないので今回はそういった部分は紹介しない。そこそこの長さの曲だけど、2ページで纏めてあるのは助かる。
・曲の構成
41にトリオと書いてあるので3部形式となる。
構成は次の通り。弱起なので、パートの切れ目が不完全小節となる。
| 1~16 | A |
| 1~16 | A |
| 17~24 | B |
| 17~24 | B |
| 25~40 | A |
| 41~48 | C |
| 49~56 | D |
| 57~64 | C |
| 1~16 | A |
ショパンは4の倍数の小節数を区切りとして曲を書くことが多く、この曲は全て8の倍数が区切りとなっている。とはいえ、これは別にショパンに限ったことではなく、音楽というものの性質上2の倍数を基本として構成することになることが多いので自然な流れである。
・アーティキュレーション
ショパンの楽譜を読むときに特徴的な解釈がある。譜例1~2の<>の形のクレッシェンド・デクレシェンドがある。これはヘアピンと呼んでいるが、「<>」はテンポ・ルバートを示している。すなわち、伴奏のリズムは一定に保ったまま右手の主旋律を引っ張ったり速くしたりとテンポを変えて歌う[1]。。
5、6各小節1拍目には「>」の形のアクセントがついているが、5は短いアクセント記号で、6はちょっと長いアクセント記号となっている。
長いアクセント記号はショパンに特有のものであり、デクレッシェンドのヘアピンを短くしたものと説明することができるのだけど、この曲ではヘアピンは上で説明した<>の形しか存在しないので、説明する必要がない。長いアクセント記号の演奏法は端的に言うとその音の音価を伸ばしなおかつ強く弾いて強調する、という意味となる。
・フレージング
この曲に限ったことではないのだけど、ショパンの曲には2小節くらいの間隔でスラーが来ていることがある。これはフレーズの切れ目で、息継ぎをするタイミングとなる。譜例のような演奏になる。この息継ぎを入れる際には決してリズムやテンポを崩してはいけない[4]。
・装飾音
ショパンのテンポ緩め系の曲によくある装飾音。
ossiaで示してある部分もあるが、単純→複雑となるように装飾していく。例えば、11は次のように書いてある。
同じ形が35と、ダ・カーポで戻ったあとの11に出てくる。全て同じ音で書かれているが、注釈にはダ・カーポ後には次のように弾かれることがあると書かれている。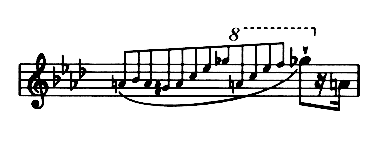
また、初期稿には、次のように書いてある。
これが最も単純になっている。
この組み合わせで、1回目11:初期稿、2回目11:通常通り、35:通常通り、ダ・カーポ11:ossiaとして演奏した。この順番はコルトー版、全音版と同じである。
同様に、7も、次のようになっているが、
コルトー版、全音版では次のようになっている。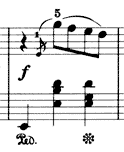
1回目だけ全音版を採用してあえて単純化して演奏している。
・半音階の運指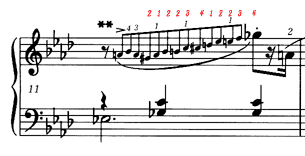
半音階の運指は指くぐりを嫌って上の赤字のように変更することが可能であるが、均質な音で弾くにはかなりの修練が必要なので、あまり勧めない。
・15小節
最初のEsの装飾音は前打音とする。普通、ショパンの装飾音は前打音にはせずに拍のタイミングに合わせるのだが、この部分では三連符のリズムが崩れてしまうので前打音とする[2]。
☆右手3拍目。重音になるが打鍵のタイミングをずらさないように。また、上の音が主旋律となるので強調する。
・Bパート
17~24がBパートとなる。ワルツを感じさせないリズムとなるため、ちゃんと3拍子でリズムを取るのが難しい。三連符とか付点のスイングリズムが入ってきて、足でリズムを取りながらでもぶれてしまう。自分でリズムを取れるようになるまではメトロノームに合わせるのが良いと思う。
・Cパート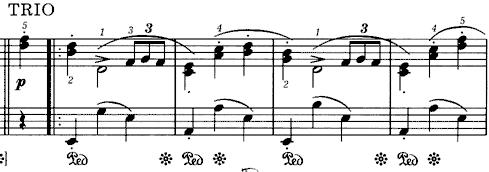
Cパートで注意しなければならないのは、2小節ごとに出てくる2拍目のDesのアクセント。割と見落としがち。いっそ、この2拍目を長く取ってアクセントにしたくなるが、短いアクセント記号なので、そういう指示にはなっていない。もちろん、演奏者が何かしらの根拠をもってこの音を長く取るというのは全然良いと思う。
・56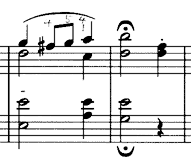
56だけだとあんまりなので、譜例は55~56を載せた。
59~55にかけて長くクレッシェンドが続いており、クライマックスの盛り上がるところだが、このフェルマータが付いている音はそれまでよりも柔らかい音で弾く[3]。
参考文献
[1]セイモア・バーンスタイン, ショパンの音楽記号 -その意味と解釈-, 音楽之友社(2009)
[2]エキエル版 ショパン/ワルツ[シリーズB], 全音楽譜出版社
[3]ショパン/ワルツ集 (アルフレッドコルトー版), 全音楽譜出版社(1999)
[4]ジャン=ジャック・エーゲルディンゲル, 弟子から見たショパン―そのピアノ教育法と演奏美学, 音楽之友社(2005)