ブルクミュラー25の練習曲より、19番アヴェ・マリア。
テンポ指定はAndantino、久しぶりにゆっくりの曲。
テンポが遅いのでかなり余裕を持って弾ける。特に苦労がなかったので、書くことがない。
・religioso
「敬虔に」という意味。英語で言うところのreligion、宗教と関連のありそうな言葉。
・ritenuto
リテヌートは直ちに遅くという意味。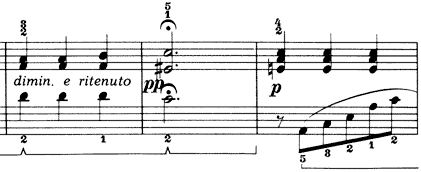
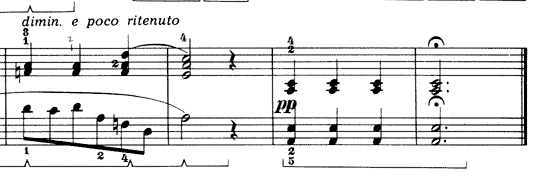
普通はa tempoなどで元の速度に戻すという指示が直後にあるのだけど、どこにもない。そのまま遅くしたままという場合もないわけではないけど、これはそういう曲ではないので、常識的に考えて続くフェルマータで一息ついたところで元の速度に戻すと解釈するべき。
それにしても、この27小節の書き方は上の段にあるのか判別しづらい。もっと下に配置するべき。
21小節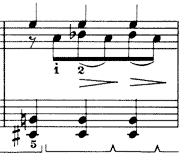
デクレッシェンドが2つならんでいる。
中声部のBABAという部分に対する指示だが、フレーズの中の相対的な音の強さを示しており、それぞれBよりもAの方を弱く打鍵するということであり、1回目のBAより2回目のBAの方を小さい音にする必要はない。
関連エントリー
20240504 18.気がかり
20240516 17.おしゃべりさん
20240322 16.ちょっとした悲しみ
20240306 15.バラード
20240224 14.シュタイヤー舞曲
ブルクミュラー25の練習曲 18気がかり
ブルクミュラー25の練習曲より18番気がかり。
楽譜は例によって全音を使う。
右手の強拍の部分が休符になっているため16部音符を均等に配置するのが難しい。24番のツバメも同様に各拍の第1音が休符となっている。この休符の所為で正確な音価を認識できずに音符と休符のバランスが崩れてしまう。スラーの部分をスタッカートにして練習するとタイミングはだいぶ改善された。
練習は拍を数えながらゆっくり始め、ゆっくりながら一定のリズムで弾けるようになったらテンポを上げるというごく普通のことしかしていないので、劇的なアドバイスとかは見当たらない。
・運指について
何故か1~3指を多用する指使いになっている。何か意味があるのだろうけど、どこにも説明がない。もしかしたら解説のされている楽譜があるのかもしれない。そんなわけで、あまり重要とは思えないので、ポジション移動の少ない弾きやすい運指に変更した。
・手元を見ずに弾く
25の練習曲集は1番から始まって徐々に音域を広げていく作りになっている。音域が広がると跳躍する距離が伸びていくので、手元を見ずに楽譜を見ながら弾くのが難しくなっていく。
跳躍の距離は手の開き具合で何度になるか体で覚えるしかないのだけど、普通に鍵盤に手を載せたときに1指:C、5指:Gに乗る形で練習を始める方が多いと思うし、ブルクミュラー25でここまで来るまでにそれなりの曲数をこなしてる筈なので、1-5指で5度の距離になるのは身に付いていると思う。同時に、その間の2,3,4指で2~4度の距離も身に付いていることになる。
次に身につける距離はオクターブである8度になる。ピアニストであれば外すとすごく恥ずかしい1オクターブの和音なので、当然掴めることを想定する。なお、この25の練習曲とかチェルニー30番は手の小さい子供も練習することを想定しているので、8度以上の和音は出てこない。
そして、5度と8度の間だが、5度よりも1音分広げたものが6度で、8度より1音狭くしたのが7度となる。ゆっくり練習している段階であれば、この距離の認識でできるが、速度を出したときはそういうことを考えずに掴められるようになってなければいけない。これはもう練習するしかない。
楽譜を見たときに瞬時に音と音の距離が分からない場合は上の運指のところの譜例にあるように楽譜に距離を書き込むと良い。楽譜を見たまま弾ければそこで立ち止まって手元を見るという必要もなくなるので、練習が捗る。
どうしても、手元を見なければならない場所ははっきりと楽譜に手元を見るように書いておく。
ここでは☆印を付けている。僕が普段楽譜に演奏上の注意点などを書き込むときに該当箇所を示すのに色々と記号を使うが、その中に☆も当然ある。こういう場合、書きやすい記号でかつ他と重複しない記号であれば良い。ついでにページの左上に「☆手元を見る」と書いている。数年後、すっかり忘れた頃にこの楽譜を見たら、この☆印は何だろ?ってなるに決まってるから。楽譜に解説を書き込むときは、他人が読んでも理解できる言葉で書く必要がある。数年後の自分は今の自分とは別の人間だと思ったほうが良い。
関連エントリー
20240516 17.おしゃべりさん
20240322 16.ちょっとした悲しみ
20240306 15.バラード
20240224 14.シュタイヤー舞曲
ブルクミュラー25の練習曲 17おしゃべりさん
ブルクミュラー25の練習曲より17番おしゃべりさん。
楽譜は例によって全音を使う。
同音連打の練習曲。同音連打というと、チェルニー30番26で散々練習した。演奏法の説明を転載しておく。
| 同音連打の演奏法 同音連打の演奏法はピアノ演奏の脱力についてというエントリーで説明したのだけど、キーを手前側に引っ掻くようにして打鍵する演奏方を勧める。離鍵した時にキーの戻る速度が速いほど次にキーを押す準備が速くできるので同音連打も速くなる。従って、打鍵後速やかにキーの上から指をどける、手前に引っ掻く奏法が有効である。できるだけ早く離鍵するために、可能な限りキーの手前の方で打鍵する。キーの端、ヘリのギリギリのところに指先がかすめるように指を振り抜くのが良い。キーのアップリフトとかを感じている余裕はない。 また、指先側にあるDIP関節、PIP関節の2つの関節を真っすぐ伸ばして固定し、指の付け根であるMP関節だけを曲げて弾くと安定する。 指がキーに対して平行になっていないと引っ掻いて指を曲げたときに隣のキーに引っ掛けてしまう。 |
この演奏法は右手の部分では使えるけど、この曲の左手では運指の都合上使えない。
左手は指使いを見て分かる通り、12121となっており、手前に引っ掻く動きは適さない。手前に引っ掻く奏法は離鍵速度が速いが、その指で打鍵するために準備するのに時間がかかるというデメリットがあるので、ここでは使えない。結局、指をキーからまっすぐ上げて離鍵することになる。
12121以外の運指も不可能ではないが、色々試した結果この指使いが最も弾きやすかった。
23~25小節
この部分の同音連打だけスタッカートがついている。
初版譜を見ると、仏初版はスタッカートがあり、独初版はスタッカートがない。出版順は仏→独なので、仏版を見て修正する形で独初版を出版したとするとスタッカートは不要となる。とはいえ、この速度で同音連打するならスタッカートで弾かざるを得ないので、ペダルを使ったりしなければ記譜上の表現がどうであれスタッカートと見做す他はない。
同音連打の後の跳躍
この曲で同音連打の後の跳躍は3度~6度の距離がある。手元を見ずに弾くためにはこの距離を体で覚えなければならない。
普通に鍵盤に手を置くとき、普通は各指を隣り合ったキーの上に置くので1-5指の距離が5度となる。ここまで来た人は多分5度までの距離は身に付いているものと思う。そこから1音分広げたのが6度である。5度から1音広げるという手順を踏まなくても6度をぱっと押せるようにしておきたい。また、楽譜を見て瞬時に音符間の距離が把握できない場合は、楽譜に直接距離を書き込んでしまうとよい。
関連エントリー
20240322 16.ちょっとした悲しみ
20240306 15.バラード
20240224 14.シュタイヤー舞曲
屋上から見える海
世界ノ全テというエロゲのアレンジCDpf ピアノフォルテに入ってた曲。タイトルの通り、ピアノを中心として、バイオリン、チェロのアンサンブルとなっている。このCDは名曲揃いなので、オススメ。CDのブックレットに全曲の楽譜が載っているのでとても助かる。
ゲームだと学校の校舎の中で流れてた曲だったと思う。ゲーム内で使われた曲よりかなりテンポを遅くしてある。
テンポの遅い曲なので余裕のある演奏ができるかと思ったけど、和音の規則性がイマイチ見いだせなくて楽譜から目が離せず苦労した。
ブルグミュラー25の練習曲 16.ちょっとした悲しみ
ブルクミュラー25の練習曲より16番ちょっとした悲しみ。
DTMやってた頃に、この曲をちょっとアレンジしたものをMIDIで公開しているけど、かなり好きな曲。声部が綺麗に別れていてアレンジしやすい。当時は、こどものブルグミュラーという楽譜を使っていて、「かわいい嘆き」というタイトルだったと思う。
1ページだけの曲がここから4曲続く。短いので譜読みが楽で良い。
楽譜は例によって全音を使う。
速度について
Allegro moderatoで結構速い。4分音符で84~90bpmとなっているが、ドイツ語初版では126bpmなので元はもっと速かったらしい。
16小節の繰り返しアリなので、合計32小節になる。4/4拍子なので、4分音符128個の長さ。126個/分で割ると128/126*60=60.95秒の長さとなる。僕の録音が59秒なので、大体オリジナルの速度になってたらしい。全然意識してなかった。
1小節目のdolenteというのは「悲しげに」という意味。ブルクミュラーはあまり見ない指示が多く、調べないと分からないことがよくある。
全体を通して難所というような部分もないが、とにかくトレモロを軽やかに弾かなければならない。この部分は何故か全く苦労せずに弾けてしまったので、よくわからないものである。チェルニー30番を真面目にクリアした成果だろうか。順番が間違ってるなあ。
結構細かく強弱の指示がある。ごく自然な強弱の流れなので、特に逆らうことなく弾くだけで効果的である。
7~9小節
8小節目1回目の"dimin. e poco riten."が2回目にはない。1回目は音量とテンポを緩めて1小節目に戻るが、2回目は7小節末尾のデクレッシェンドのまま8小節入り、9小節でいきなりpになる。
15~16小節
最後、テンポも強弱も変化なくあっさり終わる。こういう部分がタイトルの「ちょっとした悲しみ」の意味に繋がる。
関連エントリー
20240306 15.バラード
20240224 14.シュタイヤー舞曲